
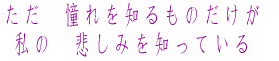
 |
僕の本棚には 学生時代に作った ガリ版刷りの 同人誌 20冊ほどと 当時のビラ数枚が 棄てられずに 残してあります。 あの時代に 活字になれなかった 散文たちを ここで やっと 活字にして あげることができました。 さとちゃん |
櫻 桃 佐藤 さと
ー生きるといふ事は、たいへんなことだ。
あちこちから鎖がからまってゐて
少しでも動くと、血がふき出す。−
〔太宰 治〕
夕方、僕は独りで呑みに出掛ける。
硬いアスファルトにカラン、カランと
下駄の音が高く響く。
便所の下駄。
まさしく僕の下駄はバイト先の便所から
盗んできたものである。
極太の黒のマジックインキで
男子便所OO書店と
書かれてある。
「居酒屋いこい」
と染められた暖簾をくぐり
僕は早速 そこのママさんに御挨拶する。
「ママさん、こんばんは。・・・」
「いらっしゃい。・・・
あら、おひさしぶり・・・。」
と
少々中年太りしたママさんが
眼を細くして応えてくれる。
そこで僕は一息入れて
他のお客さんに聞かれないように
小声でママさんに言う。
「今日は、1500円しか持って無いんです。
先に渡しておきますから、出そうになったら
止めてください。」
ママさんは、こっくり頷き、
「だいぶ、慣れたね。」
と
僕の肩を叩いて笑う。
十脚位あるカウンターの席は
既に四、五人のお客さんで
まんなかを占められていた。
僕は独りで来たので
一番端しの椅子に座る。
これで この店に来たのは
五回目だろうか。
頬杖をつきながら思い出す。
一回目と二回目は
郷土研究会の先輩と一緒に呑み
おごってもらった。
三回目は友から金を借りて
文藝部の一回生と
一緒に呑んだ。
四回目は独りで出掛けて
呑みすぎた。
意識不明になってしまい
一晩 店の二階の座敷で
横になっていた。
ママさんはちっとも嫌な顔もせず
僕の吐いた汚物を
拭いてくれた。
「さて、何にしましょうか?」
と
白いおしぼりをカウンターの向こうから
ママさんが僕に手渡す。
「あ、忘れてた。ビール一本。あとから
お銚子二本。おでん一皿。」
地下鉄鶴舞線の工事が始まってから
大学のすぐそばにあるこの店では
学生が寄り付かなくなったと聞いていた。
なるほど
今夜のお客さんは
僕を除いてすべて
すべて地下鉄工事で働く
労働者ばかりであった。
酔いのせいかも知れないが
赤銅色に焼けた首筋が光っている。
Yシャツを捲り上げた腕の
剛健さ。
言葉も ここらあたりではなさそうだった。
それにしても
皆、大きな声で話すものだ。
店で流している有線放送の音楽も
聞き取れないほどである。
「なあんだぁ。おまえも北海道かぁ。
おれも北海道から来たんだ。
俺は苫小牧だぁ。
おまえはどこからだ。?
歳はいくつだぁ。?」
四十位の男が
若い男に向かって尋ねる。
「へーぇ。親父さんも。北海道。
俺ァ、旭川から。
もうじき 二十二さ。」
「旭川は苫小牧より うんと
しばれるだろが・・・」
「そりゃぁ、しばれるってなんの・・・・。」
と若い男は
自分の首を両手で締め上げるような
仕草をして見せた。
「おまえの飯場は、どこだ。?」
「俺ァンとこは、大成建設。」
「俺は、銭高組。・・・・
おーいママさん。
この若いのに一本やっとくれ。」
僕は、そんなやりとりを
見ていると、ひどく悲しくなるのだ。
泥と汗にまみれて
生きるために働くこの人たちから
僕は生きるという行為の
哀しみを
見せつけられるのであった。
独り、俯いてビールを
呑んでいる僕のそばに
痩せ細った小柄な男が
ふらふらしながらやって来て
僕に にこやかに
話かけてきた。
「君はどこから・・・?」
「僕は名城です。
この店のすぐ裏の大学生です。」
僕はあまり
お客さんとしゃべる方ではなかった。
「ほう。インテリゲンチャさん。
しっかり勉強しなさいよ。
僕みたいにならないように・・・・。」
「そんなこと、ないですよ。
僕はインテリにはなりたくないんです。」
「いやぁ、ダメだよ。
僕みたいになったら
おしまいだ。」
両目から泪が滲んでいるように僕は思えた。
「おじさんの故郷は、どこですか。?」
「僕は東京。」
と、言っても八丈島なんですがね。」
と
虫歯だらけの前歯を見せて
ハハハと笑った。
「東京の地下鉄も僕が掘ったんだ。
僕は地下鉄専門で
地下にもぐってばかりのモグラ生活。
だから、顔も白いんですよ。ハハハ。」
「・・・・・おじさん。
奥さんは八丈島にいるのですか。?」
と僕が聞くと
「女房には、逃げられたよ。
五年前。
僕の甲斐性なしに呆れたんでしょうね。」
と、いっそう にこにこ と笑う。
ー逃げられた。−
全くこの人は正直な人だ。
僕みたいな赤の他人に自分の恥部を
曝さなくてもよいものなのに・・・。
僕は何故か楽しくなってきた。
「学生さん、歌を一曲、唄っておくれよ。」
と、八丈島の人が僕にビールをすすめる。
僕もそろそろ酔いがまわってきた。
僕は
「リンゴの歌」
を歌いだした。
「赤いリンゴにくちびるよせて、
黙って見ている青い空・・・・」
八丈島の人も手を打ちながら
歌いだした。
ママさんも、ほかのお客さんも歌っていた。
歌い終わると拍手で店が一杯になった。
「おい、学生さん。何でこんな古い歌 知っているんだ。」
と、先ほど大声で 俺も北海道だと言っていた
親父さんが
驚いたように僕をみつめている。
「はい、うちのおっかさんがよく歌っていたので・・・・
憶えてしまったらしいです。」
と、応えると
「よし、気に入った。ママさん。・・・
この学生さんにも お銚子一本、あげとくれ。」
ひどく 喜んでいる様子だった。
遠慮なく 僕はお銚子一本をいただいた。
「両親は大切にしなぁ。
親は大切になぁ。」
と言い、
親父さんは僕に背を向けて、
再び仲間と 酒を呑みだした。
ビール一本半と、お銚子五本くらい呑んだのだろうか、
もう、酔いはすっかり身体全体に回っていた。
すると、突然、
チリ チリ チリンという涼しい鈴の音が
したかと思うと、
にゃん
という猫の鳴き声がした。
僕はひょいと 足元にいる仔猫を抱き上げ
膝の上にのせた。
そして
おでんの皿からチクワを半分ちぎって
食べさせてやった。
仔猫の身体のぬくもりは快かった。
柔毛〔にこげ〕と呼ばれている
仔猫の胸のあたりを指で撫でていると
カウンターの奥の扉から
小学校一、二年生くらいの少女が
こそこそと店に出てきた。
ー仔猫を連れ戻しにきたのであろう。ー
僕はそう思い、
仔猫を少女に手渡してあげた。
しかし、どうしたことだろう。
この少女は仔猫を
僕の膝の上にのせるのであった。
ぱっちりとした大きい目を輝かせ
少女は言った。
「その、猫、抱いていても、いいよ。」
くるりと反転して少女は
奥の扉の方に戻っていった。
僕はよっぽど
人恋しそうに仔猫を撫でていたのであろう。
少女は見ていた。
知っていた。
ー酒を呑む人は いつもさびしい。ー
「ママさん。 あの子、ママさんの子。?名前は?」
「桃子というのよ。」
「ママさん。桃ちゃんは、いい娘になるね。」
「ええ、そりゃぁ、私の子だからね。」
とママさん 嬉しそうに話す。
「さくらんぼ のような 頬 していたよ。」


〔二十歳〕
|
次頁へ |

